「紫紺のジャージ」そして「前へ」――。これらの言葉を聞けば、誰もが大学ラグビー界の伝統校、明治大学ラグビー部を思い浮かべるでしょう。重厚なフォワードを武器に、愚直に前進を続けるその姿は、長年にわたりファンを魅了してきました。しかし、その圧倒的なパワーの裏側には、単なるフィジカルの強さだけでは語れない、驚くべき哲学、劇的な出来事、そして乗り越えるべき課題が隠されています。本記事では、現在の明治大学ラグビー部を形作る、知られざる5つの事実に迫ります。
練習は1日2時間。強さの土台は「残りの22時間」で作られる
明治大学ラグビー部の強さを支える根幹の哲学は、一見すると直感に反するものです。それは、1日わずか1~2時間の練習時間ではなく、グラウンドを離れた「残りの22~23時間」にこそ、強さの土台が築かれるという考え方なのです。
この「オフ・ザ・ピッチ」を重視する規律は、丹羽政彦元監督によって確立され、田中澄憲前監督が継承、そして現在の神鳥裕之監督へと受け継がれました。この哲学を確立した丹羽元監督は、自ら部員寮に住み込んで日常生活の規律向上に努めたほどです。このアプローチは、大学選手権9連覇を達成した絶対王者・帝京大学が日常生活の規律を徹底していたことに着想を得たもので、フィールド外での自己管理が、試合中の冷静な判断力とプレーの質に直結すると考えています。
神鳥監督は、その重要性を次のように語っています。
たとえば24時間あったら練習でグラウンドに立つ時間は1、2時間くらいで、22、23時間はラグビーと関わっていないですよね。そこで普段から正しい選択、判断が出来るようなクセを付けておくと、グラウンドの中で理性を保ったままプレーができたりします。僕はそこを大事にしてチームを作りたいと思っているんです。
「銀河系軍団」の意外な弱点? 課題は“劣勢時のメンタル”
全国の強豪高校からトップクラスの才能が集まり、その豪華な選手層から「銀河系軍団」とも称される明治大学。しかし、その圧倒的なタレント力とは裏腹に、乗り越えるべき明確な弱点を抱えています。
専門誌『ラグビーリパブリック』の戦力分析によると、チームが直面する最大の課題は「劣勢時の対処」だと記載されています。6月の帝京大学戦(0-31)や8月の同カード(21-28)、そして筑波大学戦(22-31)で見られたように、「一度ペースを奪われると活力を失いがち」という傾向が指摘されているのです。
個々の選手のスキルは他大学を圧倒するものがありながら、チーム全体として逆境を跳ね返す精神的な強さが求められています。この事実は、ラグビーがいかに才能だけでは勝利できないスポーツであるかを物語っており、チームが向き合うべき核心的なテーマとなっているのです。
たった一言のスローガン「完遂」に込められた、鉄の意志
今季、明治大学ラグビー部が掲げたスローガンは、たった一言、「完遂」です。
この言葉には、「与えられた役割を完全に成し遂げる」という意味が込められています。公式発表によれば、このスローガンは、チームとしても個人としても、試合終了のホイッスルが鳴る最後の一分一秒まで一切の隙を見せず、自らの役割を完璧にやり抜くための強いメンタルを築き上げるという決意の表れです。
これは、奇しくも前述した『銀河系軍団』が抱える“劣勢時のメンタル”という課題に、正面から向き合うスローガンと言えます。単に「勝利」を目指すだけでなく、完璧な実行力と精神的な持久力を追求する厳格なプロセスに焦点を当てている点に、王者奪還にかけるチームの鉄の意志が感じられます。
100回目の伝統戦、奇跡の幕切れ。勝利を呼び込んだのは“敵将の勘違い”
近年の明治ラグビーを語る上で、ライバル慶應義塾大学との記念すべき100回目の伝統戦は外せません。試合は一進一退の激しい攻防が繰り広げられましたが、その幕切れは誰もが目を疑う、まさに奇跡としか言いようのないものでした。
最終スコアは24-22で明治大学が勝利。しかし、その瞬間は予期せぬ形で訪れました。試合終了間際、リードされているにもかかわらず、慶應義塾大学の主将が自チームが勝っていると勘違いしてし、時間を使い切るためにボールをタッチラインの外へ蹴り出し、自ら試合を終了させてしまったのです。
会場が騒然とする中、明治大学の劇的な勝利が確定。フィジカルと戦略がぶつかり合う激しいスポーツにおいて、たった一つの判断ミスが歴史的なライバル対決の行方を決定づけるという、ラグビーの奥深さと残酷さを示す象徴的な一戦となりました。
「帝京一強」は終わった。ライバル早稲田と築く「早明新時代」
大学ラグビー界は長らく、大学選手権9連覇を成し遂げた帝京大学が君臨する「帝京一強」の時代が続いていました。しかし、その構図は過去5年ほどで大きく変化しています。
2017年度以降、大学選手権の決勝には必ず明治大学か、その伝統的ライバルである早稲田大学のどちらかが進出しており、現代の大学ラグビーは「早明新時代」を迎えたと言われています。過去の歴史では、どちらかが黄金期を迎え、もう一方が低迷する時代が多くありました。しかし、現代の早明関係を特徴づけるのは、その「実力が拮抗し」ているとう点です。
連勝することが極めて難しい、手に汗握る実力伯仲のライバル関係は数十年来で最も競争的で均衡が取れたものとなっており、大学ラグビー界の中心的な物語となっているのです。
まとめ
グラウンド外での哲学が、グラウンド内の精神的課題を克服するための鍵となります。明治大学ラグビー部は、その強大なフィジカルのイメージ以上に、複雑で多層的な挑戦の只中にいるチームです。才能あふれる「銀河系軍団」が日本一の座を目指す旅は、もはや単なる力の勝負ではありません。それは、「残りの22時間」で培った規律と、「完遂」という鉄の意志が、劣勢でこそ試されるメンタルの壁を打ち破れるかどうかの証明の物語なのです。
才能、哲学、そして時に運。全てを味方につけた紫紺のジャージは、再び大学の頂点に立つことができるのでしょうか。
今シーズンも明治大学ラグビー部から目が離せません。
以上です。
ご一読ありがとうございました。
 |
新品価格 |

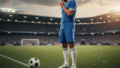

コメント